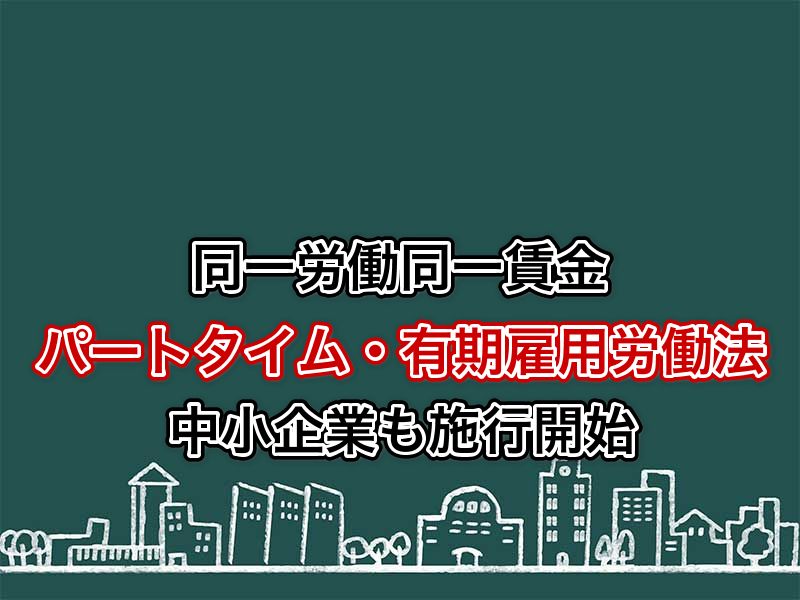目次
中小企業でのパートタイム・有期雇用労働法が施行開始
2021年4月より、中小企業でのパートタイム・有期雇用労働法が施行開始となります。大企業では、既に1年前の2020年4月から施行されている法律です。
働き方改革で「同一労働同一賃金」の言葉を聞かれていると思いますが、この「同一労働同一賃金」のもとになっている法律です。
では、「同一労働同一賃金」とは?
・非正規社員と正社員の不合理な待遇差を禁止するものです。
非正規社員の責任の程度や仕事内容・人事異動や転勤の範囲などが正社員と異なるとき、異なる待遇とすることは問題はありませんが、不合理な待遇差は禁止されます。バランスの取れた待遇差は良い、不合理がだめということです。
この不合理ということは、「理由がない」「説明できない」ということになります。
例えば、「正社員は〇〇という理由でボーナスがある、〇〇という理由で手当がつく、パートは〇〇という理由でボーナスがない、あっても〇〇という理由で額が異なる」のように合理的な説明ができることが求められます。
従来は、パートだから〇〇手当はつかない、正社員じゃないからボーナスが出ないというような、合理的な理由がないケースは見直しが必要です。
同一労働同一賃金で見直しすべきポイント
非正規社員と正社員の待遇差については、基本給、ボーナス、退職金、各種手当と個別に見直していく必要があります。
特に違法とされる可能性が高いケースは手当関連で、重点的に対策していく必要があります。
- 皆勤手当の格差
- 通勤手当の格差
- 家族手当の格差
- 住宅手当の格差
精勤手当、皆勤手当について
正社員には支給しているのに、契約社員やパート社員、定年後再雇用社員には不支給であるケース。
家族手当、扶養手当
正社員には支給しているが、契約社員には不支給である。
ただし、定年後の再雇用嘱託社員への不支給は、違法となる可能性は低い
住宅手当
転勤の範囲等に正社員と差がない契約社員への不支給は違法となる可能性が高い。
転勤の範囲等に正社員と差がある契約社員への不支給は、合理的な差であれば違法とはならない。
ただし、定年後の再雇用嘱託社員への不支給は、違法となる可能性は低い。
賞与、退職金、基本給
違法となるリスクは比較的小さいが、賞与、退職金、基本給に待遇差がある会社では、
- 職務内容の違いの明確化
- 配置転換の範囲の違いの明確化
- 正社員への登用
などの対策が求められます。
企業は手当の見直しや、賃金規定の改訂などの対応が必要
前述のように、違法となる可能性の高いものについては、見直していく必要があります。
賃金以外の部分の見直し
- 非正規社員の中でも正社員と同様の仕事をしている人は、正社員に登用する
賃金制度の見直し
- 正社員に通勤手当や精勤手当、家族手当を支給している場合は、契約社員にも支給する
- 趣旨不明確な手当は趣旨を明確にする
- 正社員に支給されているが、非正社員には支給されていなかった手当の廃止を検討する
ただし、正社員の手当の廃止等は不利益変更に該当する可能性があるので、経過措置と話し合いが重要となります。
(例)経過措置を設けながら、手当を基本給に組み入れていくなど
雇用契約書・労働契約書
雇用する際に交わす、雇用契約書・労働契約書で、労働条件を区別していくことが大切です。
例えば、勤務地、勤務時間、追加するなら、期待すること、責任の範囲、転勤、配置換えなど明確に区別できる条件を含めておきます。
就業規則の見直し
条文の適用範囲に注意して見直しをかけます。つまり主語が「従業員」なのか「正社員」なのか。就業規則に断りがなければ、正社員、パート社員、契約社員、嘱託社員の全てに適用されます。
ですので正社員の就業規則と、パート社員、契約社員の就業規則を分けて作成するのが良いのですが、別れていなくても就業規則の条文に、どの身分の社員に適用するのかを明示しておく必要があります。
罰則は無い?
現時点で、同一労働同一賃金に守れていなくてもも罰則はありませんが、行政指導が入る恐れがあります。
また、非正規社員から損害賠償請求を受けるリスクがあります。最高裁まで争われた判例など過去の判例から1人100万円程度の損害賠償が想定されます。
中小企業の4月施行開始まで間がありませんが、従業員の棚卸しをし、就業規則、賃金規定を見直し、必要に応じて改訂し備えておきましょう。
正社員と非正規社員の待遇に差がないのであれば、正社員化されることも選択肢の一つです、キャリアアップ助成金の正社員化コースに適用できれば、助成金を受けることができます。